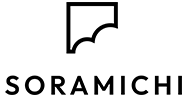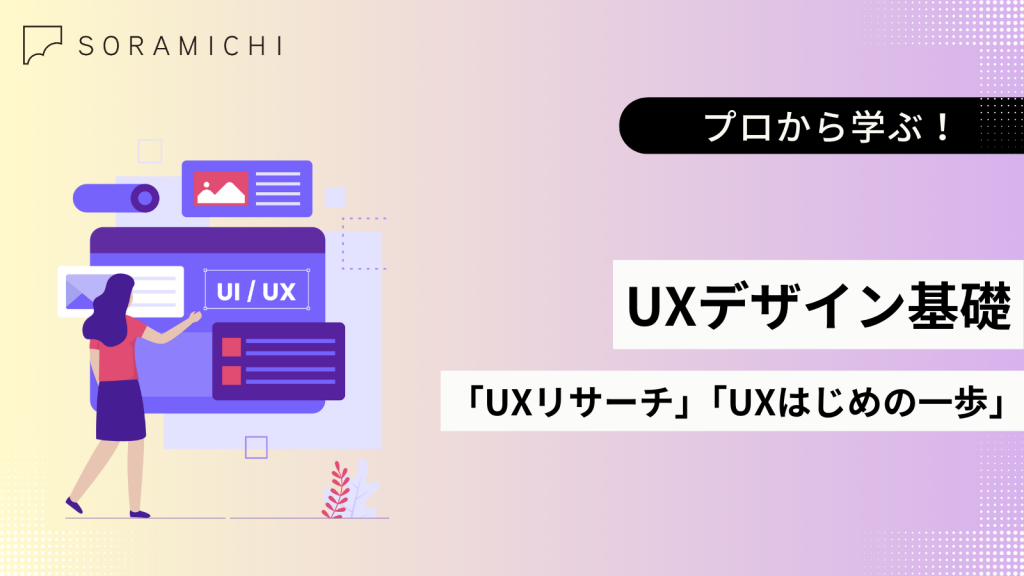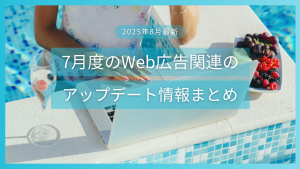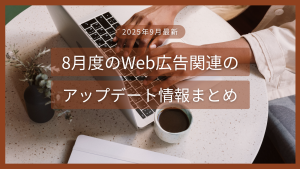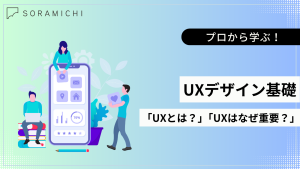プロから学ぶ!UXデザイン基礎・UX組織を作る「UX成熟度段階モデル」【YouTube動画まとめ記事】

この記事では、ソラミチの顧問の丸山潤さんによるUXデザインの基礎についての解説動画の内容をまとめています。
今回のテーマは、UX組織を作るためのフレームワーク「UX成熟度段階モデル」です。
丸山さんのお話を全部聞きたいという方はYouTube動画のご視聴をおすすめします。
そもそも、なぜUX組織を作るのは難しいの?
ここ数年で、日本国内でもUXに取り組む企業や組織は増えてきました。しかし一方で、「UX調査を行ったが、他部署を説得できなかった」「予算がおりなかった」など、企業内におけるUXへの理解が思うように深まらないケースも少なくありません。
ユーザー中心の考え方が根付くUXへの理解や成熟度は、企業の成長に大きな影響を与えます。「UX成熟度段階モデル」について解説する前に、まずは企業や組織内において、UXへの取り組みを円滑に進めていくためのポイントをおさえていきましょう。
ビジネス側とUX側の対立
UX組織を作るときには、必ずと言っていいほど、ビジネス側とUX側での対立が発生します。
ビジネス側は、UXに欠かせないユーザーの行動や思考の土台となるメンタルモデルの理解が備わっていない状態で、UX側に「とにかく早く作って欲しい」と要求しがちです。
一方でUX側は、ビジネス側がUXを理解してくれないことに不満を募らせます。またUX側にも、「本に書いてあるとおりのことができるはずだ」という思い込みがあるため、摩擦が起きてしまうのです。
両者の対立を解消するために作られた「UX成熟度段階モデル」
「UX成熟度段階モデル」は、先に解説したような、UX組織を立ち上げる際に発生する対立構造を解消するために作られたフレームワークです。「UX成熟度」とは、組織全体がどの程度UXに取り組んでいるかを測る評価基準のことを指します。
6段階で評価できる「UX成熟度段階モデル」を活用し、自社組織のどの段階にあるのかを正確に判断することができます。自社組織が今いる位置が明確になれば、UX組織を構築する上で何をすべきかも、自ずと見えてくるでしょう。
UX成熟度段階モデル
UX成熟度のフレームワークは、1~6段階に分かれます。私のnoteでも紹介していますが、各段階の状態について見ていきましょう。
UX成熟度段階1:拒否
UX成熟度段階1は、UXに対して「必要ではない」「重要ではない」「空想上の用語である」と考えている状態です。
UX成熟度段階2:限定的
UX成熟度段階2は、「UXが重要であると一部の人が考えている」という状態です。組織内の少数メンバーはUXを理解し、価値も感じています。
UX成熟度段階3:新興
UX成熟度段階3は、一部の人はUXが非常に重要だと考え、プロジェクトの一部では実装を行っているものの、施策に一貫性のない状態です。
UX成熟度段階4:構造化
UX成熟度段階4は、企業や組織内でUXに対する価値や信頼が広がり始め、部分的にはシステム化されている状態です。
UX成熟度段階5:統合的
UX成熟度段階5は、ほぼ組織として出来上がっている状態で、UXがビジネスや組織戦略の中核になっているという認識を持っています。
UX成熟度段階6:統合的
UX成熟度段階6になると、当たり前のようにUXが実装され、UXが組織のDNAに組み込まれている状態となります。
UX成熟度段階モデル フレームワークの方法
フレームワークで重要なことは、自分たちがどの段階にいるのか理解することです。
書籍に載っているような方法は、実は初心者向けではありません。ほとんどの書籍はUX成熟度段階モデルでいうと4~6程度のレベルに達してようやく理解できる内容で書かれており、1や2の段階にいる人にとっては受け入れも難しい内容です。
では、どのようにレベルアップしていけばいいのでしょうか。
UX成熟度1:小さな一歩から始める
組織としてはUXへの取り組みがまだ何も行われていない状態のUX成熟度1では、当然ながら予算もありません。この状態からUX成熟度2へレベルアップするために重要なのは、実現可能な小さな取り組みから始めることです。
例えば、外部の専門家を招いての講習会など、学習機会を作ることも良いでしょう。教科書通りのことを取り入れるのではなく、自分たちの企業や組織に合った小さな成果を積み重ねることがUX成功への第一歩となります。
また、UX成熟度1では、UXにおけるメンタルモデルを理解することも重要なポイントです。まずは少ない工程数で社内の人間にUXに触れてもらい、意見を出し合いながら、思い込みに気づく機会を作りましょう。
UX成熟度2:投資判断として重要視されていることを知る
UX成熟度2では、一部のメンバーにUXの理解が広まっているものの、あくまでも自分たちのための実験としてスタートし、行き当たりばったりになっています。また、UX戦略の策定において重要な「ユーザーニーズ」や「行動」がビジョンの軸にないため、継続的な投資も行われていません。
つまり、UX成熟度2からレベルアップするためには、投資判断の決定者にUXの価値を理解してもらうことが欠かせないでしょう。そのためには、限られた予算とスケジュールの中で、効果的なUXプロセスを厳選し、実行していくことが重要となります。
具体的には、意志決定を行うトップが、何を重要視しているのかを知ることです。例えば「ユーザビリティテストで〇〇の使い方が悪いから売上も低いのでは?」という指摘があれば、指摘部分を徹底的に行います。あるいは、「そもそも本質的なニーズを捉えられていないのではないか」という指摘があった場合には、ニーズのヒアリングを行う必要があるでしょう。
全プロセスを実行したい気持ちがあっても、この段階では投資してもらえないため、組織のトップが課題として感じていることに対し、ピンポイントで効果を出していくことが次へとつながります。
UX成熟度3:ResearchOpsを導入する
UX成熟度3では、一部のチームが実際に取り組み始めていますが、全体的に知見が不十分で一貫性はなく、ユーザー中心の考え方も浸透していません。
ここで導入してもらいたいのが、ResearchOps(リサーチオプス)です。ResearchOpsとは「UXリサーチを円滑かつ効果的に進めるための仕組みと管理」を指す概念で、具体的には人材・プロセス・ツール・戦略などが当てはまります。
<ResearchOpsの業務について>
- リサーチ対象者の管理業務(スクリーニングや日程調整など)
- ガバナンス業務(個人情報取り扱いに関するガイドライン作成など)
- ナレッジマネジメント業務(リサーチ結果の共有とリポート管理など)
- UXリサーチで使用するツールの管理業務
- UXリサーチチーム以外のメンバーの教育業務
- UXリサーチの価値の伝道
ResearchOps業務の中でも、5・6は特に重要です。UXは想像以上に複雑なため、実際に体験してもらわないと、想像上のUXの思い込みが外れません。例えば、UXリサーチャーのインタビューに同行したり、UX理論のワークショップを開催したりなど、教育体制を整えると良いでしょう。
また、UXのメンタルモデルも、ResearchOps5・6の段階で非常に重要になってきます。思い込み状態での仮説を持っている状態で、「自分の仮説は間違っていた」ということを体験することが理解を深めるカギとなります。
UX成熟度段階4:各チームでビジョンを共通認識として落とし込む
UX成熟度段階4では、UXの価値や取り組みを組織全体が理解しているものの、ユーザー中心の考え方が全体に浸透していないことが課題です。
従って、この段階からレベルアップするためには、各チームにビジョンを共通認識として落とし込み、ビジョンに沿った役割を理解した上でUXプロセスを計画・実践していくことが重要になります。
UX成熟度段階5・6:完成状態にあり、経営層主体でUXを推進
UX成熟度段階5は、ほぼ完成状態にあり、5と6は常に行き来することになります。レベル5の状態としては、組織全体でUXへ取り組み、結果も良好、UXが戦略の一つとなっているため、成熟度としては十分達成しているといえるでしょう。
UX成熟度段階6に到達する組織はほとんど例がありませんが、目指すとしたら、組織のトップである経営層が主体的にUXの推進を行い、企業の経営方針として取り組むことがポイントです。
従って、5から6は経営層がどのようにUXと向き合っていくかで変わります。UX成熟度段階6は、組織の全員がユーザー中心の考え方を理解、実践している状態です。戦略策定や意思決定、システム内の開発に至るまで、すべてにUXが取り込まれており、組織のDNAとしてUXが根付いています。
さらに、UX成熟度段階6を維持することも重要です。上層部がUXへの取り組みについて話し合い、企業内の文化として定着させていく必要があるため、自ずと長期的な事業方針にUX関連の指標も盛り込まれるでしょう。
成熟度1~3の会社は何から始めるべき?
現在、日本国内のほとんどの企業がUX成熟度段階1~3に当てはまります。では、成熟度1~3の企業は、まずどのようなことから始めるべきなのでしょうか。
ユーザビリティテストを例にあげると、全てのフローを完璧に行う必要も、丁寧に分析する必要もありません。多くの人が、「ユーザビリティテストでは課題分析を細かくしなければ」と思いがちですが、初期段階では細かい分析よりも明らかな改善ポイントに着手することが重要です。
実際にユーザビリティの考えを作ったヤコブ・ニールセンも、小規模のユーザビリティテストの回数をこなす方が質が上がると提言しています。ユーザビリティテストとは、3ヶ月に一度のユーザビリティテストで時間をかけて分析するよりも、雑な内容であっても1週間に何度も行うことで効果を発揮していくものです。
UX成熟度が上がると事業にはどう影響する?
それでは、実際にUX成熟度が低い状態から高い状態にレベルアップしたケースでは、具体的にどのような影響があったのでしょうか。
結論から言うと、組織全体で何を目指しているのかが分かるようになるため、プロダクトへの理解が深まり、チームに一体感が生まれます。
戦略フェーズにおいて最も重要な基礎となるのは、ユーザーニーズへの理解です。UX成熟度段階4や5で、全員がユーザーニーズを理解している状態になると、チームのコミュニケーションが非常に円滑になり、プロダクトへの想いも変わります。
実際に私がアドバイスをしている企業でも、初期段階では黙っていたエンジニアの方々が、プロダクトへの理解が深まるにつれて発言がどんどん増えていきました。
まとめ
アメリカのビックテック企業などUX成熟度が高い組織は、ビジネスの戦略にUXを取り入れ、本質的なユーザーニーズを理解しています。
まずは自分たちの組織の状態が「UX成熟度」の段階でどこに位置しているのか、成熟度を上げるには何をすればよいのかを知ることから始めてみましょう。
この記事を書いた人