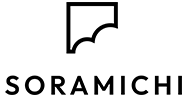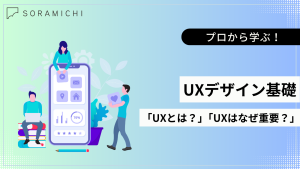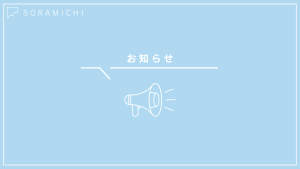プロから学ぶ!UXデザイン基礎「UXリサーチ」「UXはじめの一歩」【YouTube動画まとめ記事】
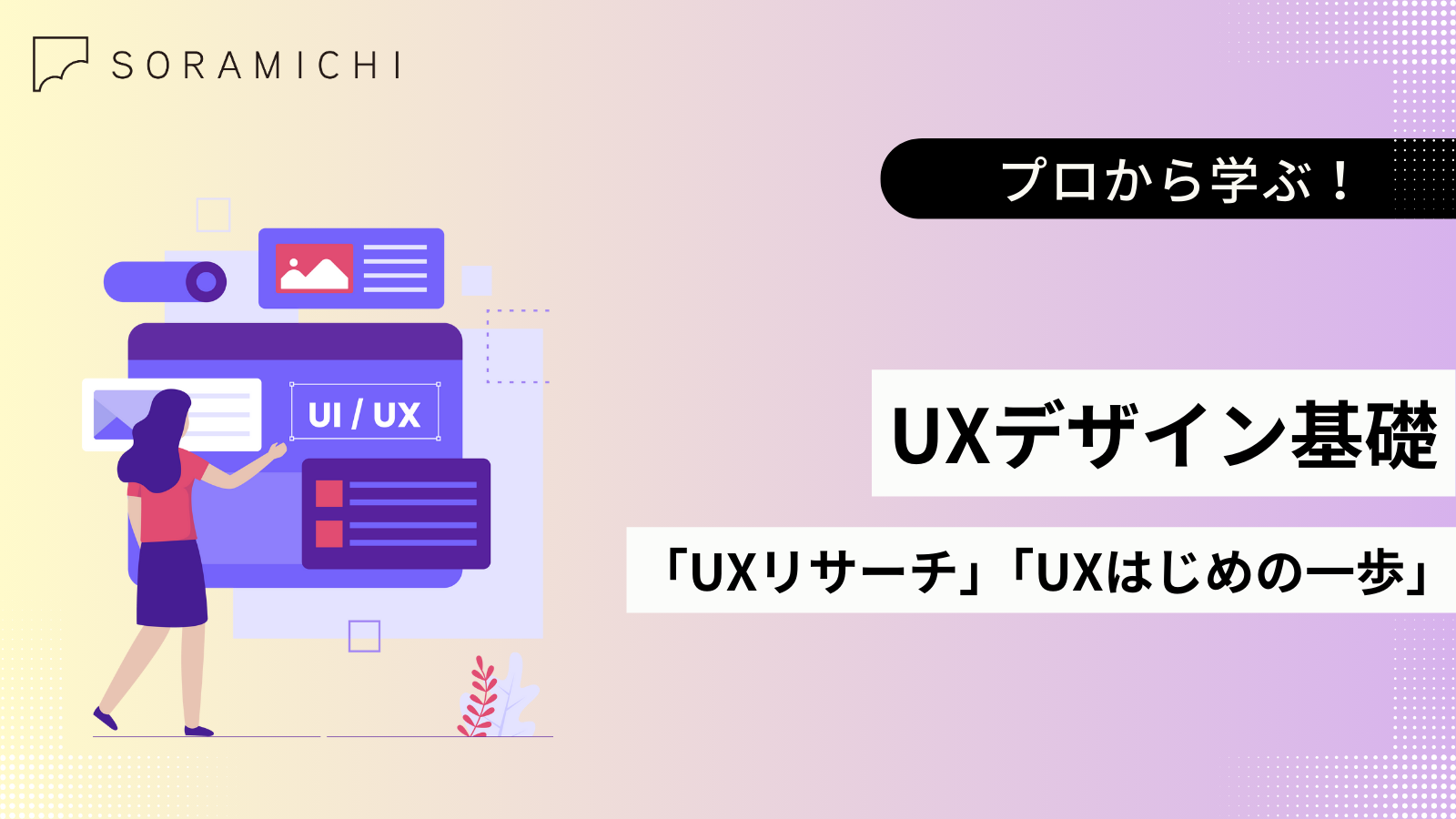
この記事では、ソラミチの顧問の丸山潤さんによるUXデザインの基礎についての解説動画の内容をまとめています。
今回のテーマは「UXリサーチ」「UXはじめの一歩」です。
丸山さんのお話を全部聞きたいという方はYouTube動画のご視聴をおすすめします。
UXリサーチとUXデザイン
UXデザインを学ぶ上で、「UXリサーチ」と「UXデザイン」は重要なポイントです。
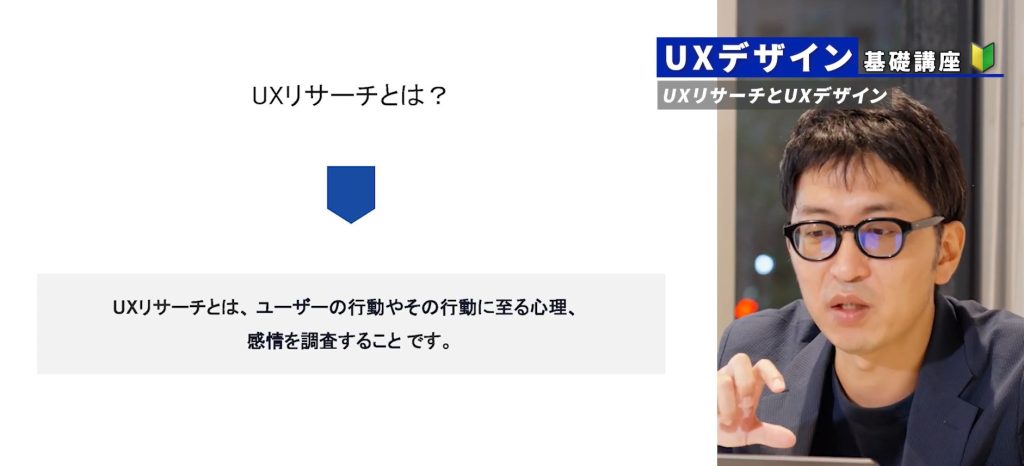
ここ数年で「UXリサーチ」という言葉を耳にすることがとても多くなってきました。「デザインリサーチ」と呼ばれることもあります。UXリサーチとは、ユーザーの行動やその行動に至る心理、感情を調査することです。UXデザイン、もっと大きなカテゴリで言うと、「デザインとは設計である」と前回のお話でお伝えしました。ユーザー体験を設計する前にとても重要なことが、この「UXリサーチ」をすることです。
ではなぜ、デザインの前にリサーチをするのでしょうか。
UX5段階モデルとは
これもよく耳にしたり書籍でも見かけるようになってきましたが、「UX5段階モデル」というものがあります。
UX5段階モデルというのは、このUX(User Experience)の要素を5つの段階に分類したものです。
1つ目の「戦略(Strategy)」は、ユーザーニーズとプロダクト目的の設定です。そこから「要件(Scope)」「構造(Structure)」「骨格(Skeleton)」「表層(Surface)」と、UIデザインやビジュアルデザインに至るまでを5段階に分類したものを「UX5段階モデル」と言います。特に海外のプロダクトが、このUX5段階モデルの要素で作られていることが多いです。
ここで、UX5段階モデルの職域と領域について紹介します。これが正解というわけではないですので、あくまで参考として下記の図をご覧ください。
UX5段階モデルでは、例えば戦略であればUXストラテジストが担当し、要件の部分はUXリサーチャーが、構造の部分はUXデザイナーが、最後の方になっていくとUIデザイナーが担当していたりと、職種によってUX5段階モデルの各部分を担当する人が存在します。
一方、日本ではUXリサーチャーとUXデザイナーを兼務するなど、海外のように担当者を細かく分類していないことが多いです。戦略から構造まで、場合によっては骨格までをUXデザイナーが担当していたりと、会社によって分類の定義が異なることは覚えておきましょう。
人の本質を知るためにUXリサーチが大切
UXデザインを設計する前には、UXリサーチで数多くの調査をする必要があります。
その理由は、設計をする前に人の本質、つまり「人が何を考えているか」ということを正しく知る必要があるからです。正しい情報を拾わないままデザインを起こしてしまうと、間違った方向に進んでしまいます。様々なリサーチの手法を駆使してUXデザインやUIデザインを設計する必要があります。
UXリサーチ手法「定性調査」「定量調査」
UXリサーチの手法として20種近くあるのですが、今回はいくつかピックアップして紹介します。UXリサーチ手法を分類すると、「定性調査(図左)」と「定量調査(図右)」の2つに分けられます。
定性調査では、ユーザビリティテスト、フィールド調査、フォーカスグループ、インタビュー、アイトラッキング、コンセプトテスト、日記調査などがあります。定量調査では、A/Bテスト、アンケート、データ分析などがあります。
例えばUXリサーチでUXデザインをするためのフレームワークとしては、さきほどのUX5段階モデルの「戦略」に近い場合、(下図左の)「アイデア創出」にあるビジネスモデルキャンバスやリーンキャンバス、バリュープロポジションキャンバスを使います。
「ユーザー分析」の場合は、ペルソナや共感マップ、カスタマージャーニーマップを使います。開発とシームレスにするためのフレームワークとしては、ユーザーストーリーマッピングや、全体のユーザーの行動を見るという目的でエクスペリエンスマップを使うなど、多種多少なフレームワークが存在しています。
案件のフェーズによって適したリサーチ手法、フレームワークを使いながら、UXリサーチとUXデザインを行っていきます。
リサーチ手法、フレームワークのカギは「期間とコスト」
ではどのようなリサーチ手法で、どういうフレームワークを使うのが良いのでしょうか。カギとなるのは「期間とコスト」です。
例えば「日記調査」は、約30日間毎日その人の行動を記録します。約1か月毎日となると、日記調査だけでも莫大な時間とコストがかかることがわかるでしょう。実際の例として、ダイソンはドライヤーを作った時、実際に美容室で働き、美容師さんがどこにストレスを感じるかということを毎日記録しました。自分たちが働いてみて、ダイソンのドライヤーで髪を乾かしているのを見て記録するということをやっていたのです。
「アンケート」も使うことが多い手法です。「どこからインタビューしたらいいかわからない」というように全体像を把握できてない時は、一度アンケートで全体感を見て、どの部分にフォーカスしてインタビューすると良いのかを検討します。
「カスタマージャーニーマップ」は、ペルソナがはっきりしている時は良いのですが、例えばGoogle検索は世界中の人が使っていてペルソナがはっきりしていないため、活用しづらいでしょう。リサーチ手法やフレームワークで何を使うかは、商材によってかなり変わると言えます。
なぜUXリサーチが大事なのか
なぜここまでUXリサーチを重要視する必要があるのでしょうか。ここでは「メンタルモデル」というものがポイントになります。
メンタルモデルとは、現実世界がどのように機能するかを模した頭の中にあるモデルであり、思考の前提や枠組みとなるものです。
要約すると「頭で考えていることは人に聞くとほとんど違うことが多い」ということです。あの人はこう思ってるんじゃないか、この人はこれが好きなのではないかと考えていることは、大体間違ってることが多いのです。
だからこそ、UXをやる人たちは自分の考えていることは間違っていることが多いと理解することが大事です。正しい情報を深掘りして、UXリサーチという手法を使い、本当のファクトを見つけていくことが大切なのです。
重要なのは本質を言語化できるまでリサーチすること
以前、金融系の案件でリサーチをしていたときの話です。資産運用の際に、顧客に「お金は欲しいですか?」と聞くと、大概の人は「生活がある程度できれば大丈夫」とか、「お父さんやお母さんのような生活ができれば」と答え、「大金持ちになりたいです」という人はほとんどいませんでした。そこで、本質的なことは本人も言語化できないという問題に直面します。だからこそインタビューなどのリサーチ手法を使って、もっと考えや想いを深堀をする必要があるということです。お父さんのような生活ができるとは結局どういうことなのか、詳しく言語化しなければなりません。
例えば年に2、3回は旅行に行きたいとか、持ち家が欲しいとか、週に1回は家族で外食に行って美味しいものを食べたいとか、色々な考え方があるでしょう。そこに行きつくまでインタビューで深堀りし、設計して、どのようなタイプの人がどのくらいの資産運用をしたいのかということを分析していくのです。これがUXリサーチで、正しく分析できると正しいペルソナが出てきて、どのような人にどのようなサービスを作れば良いかということが解ってきます。大事なことは、自分の思い込みではなく仮説を立てて相手にぶつけ、正しい情報を出していく作業を行うことです。
「正しい」はどのように判断するか
それでは「正しい情報」とはどのような情報でしょうか。リサーチによって何が正しいかを理解するのは簡単なことではないでしょう。
UXにおいて、リサーチやデザインをする人達はあくまでその作業をする人であって、「何が正しいか」は「UX」に関わるプロダクトチーム全員で取り組むべきことです。だからこそ、リサーチ結果を経てチーム全体が「これだ」と確信を持てるかどうかが大きいのです。
そのためには「ユーザーニーズ、目的・ゴール設定」が大事なポイントとなります。ここでメンバー全員が「このサービスはこれがコアな部分だ」と思えるかどうかです。
「ユーザーニーズ」では、バリュープロポジションキャンバスというフレームワークを用いるのですが、それがメンバー全員が確信を持って出来上がった状態なのかということです。
※バリュープロポジションキャンバス…自社の製品やサービスと顧客のニーズを表したもの。誰に何を提供するのか、顧客のニーズ、顧客に対して提供できる価値を書くことで、自社と顧客とのズレを認識します。
UXデザイン はじめの一歩は「小さく回す」
UXリサーチやUXデザインをやる時に、壁にぶつかる人が最近本当に多いと感じています。ここで、私のnoteの記事「UX成熟度とは?ユーザー中心組織をつくるために段階別にすべきこと」から紹介したい話があります。
AppleのUXデザインなどを手がけたアメリカの「ニールセン・ノーマン・グループ」によると、UX成熟度段階モデルというものがあり、1から6の段階別に何をやるべきかということを書いています。
例えば、「1.拒否」は全く取り入れないと言っている人、「2.限定的」は取り入れ始めたという人です。
UXにおいて、この「2.限定的」の段階でうまくいっていない企業が多いと思っています。このフェーズは、手法や理論に囚われずに、まずはユーザーもしくはカスタマーの声を聞く習慣を作ろうという段階です。ユーザビリティテストを1つするにしても、設計や分析に時間をかけると結局2ヶ月、3ヶ月かかってようやくテスト結果が出るという状況になります。ですが、まだUX成熟度が組織で高まっていない時にこの状態になってしまうと、経営者から「投資対効果が悪い」という話が出て、UXの価値に気づいてもらえないということが多いのです。
初めの段階ではまず、なるべく手法や理論に囚われずにユーザーの声を聞き、分析もなるべく時間をかけず、わかったことを逐次反映してスピーディーにやるということが重要です。
ニールセン・ノーマン・グループのヤコブ・ニールセンは、「3ヶ月に1回ユーザビリティテストをするより、特にプロダクトが出来上がっていない時は1週間に12回細かくテストした方が品質は上がる」と言っています。ヤコブ・ニールセンが言うように、UXデザインのはじめの一歩は、小さくたくさん回すことに注力することをおすすめします。
ユーザーの体験を知ることが大切
ではUXにおいて、はじめの一歩として具体的に何から始めると良いのでしょうか。はじめの1歩としてまずやることは、ユーザーの体験を知ることです。ユーザーと話をするだけでも自分たちの理解が変わる事が多いです。
例えばユーザーと週に1回、面談やインタビューのような形式でミーティングするのも一つの方法です。他にも、実際に自分たちのプロダクトを触ってもらって感想を聞くとか、ユーザビリティテストとして、サービスを触ったことのない人に最初のログインのところから触ってもらっているのをカメラ越しに確認するなど、様々なやり方があります。
そんなに売れているサービスではないけれど使い込んでいるユーザーがいる場合は、どういう点でそのサービスに惚れ込んでいるのかをきちんと聞いてみる。「なぜこの人たちはこんなに惚れ込んでいるのだろう」と、プロダクトを作る側がその視点に気づいておらず、マーケティングで打ち出せていれば売れていたであろう事例もありました。
サービスを触ったことがある人とない人、触ったことはあるけど使わなくなった人など、ユーザーの立場によって感想は変わるでしょう。したがって、あらゆるタイプのペルソナで分類して、なぜこの人は離脱したのか、どんな問題があってこのサービスから離れてしまったのかを聞くことが有効です。
世界で高まるUXリサーチの力
Googleでは、Googleマップだけで世界各国に85名のUXリサーチャーという人たちを置いて調査しているそうです。それだけでUXの重要性が高まり、なぜ日本人がGoogle検索を使うのかといったところも考えています。
オンラインストレージサービスを提供するDropboxは、GoogleドライブやOneDriveなどの競合がいる中でDropboxが1兆円企業になるまでに成長したのは、UXリサーチでUXの地道な改善をしたことによるものでした。
まとめ
プロダクト開発を成功させるためにはUXが必須で、ぜひチャレンジしてほしいと思っています。UXリサーチはユーザーの本質的なニーズを正しく理解し、最適なデザインをするための重要な土台となります。
スケジュール、コストなど、案件や状況によって適切なリサーチの手法やフレームワークを検討し、プロダクトの精度を高めることが成功へ近づきます。まずは小さく実践し、あらゆるユーザー体験を拾いながらUXデザインを進めていきましょう。
この記事を書いた人